×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
安達かずみです。
清川妙著『兼好さんの遺言ーー徒然草が教えてくれるわたしたちの生きかた』を読みました。
徒然草の言葉を手本に、生きてきた作者の体験が、徒然草を分かりやすく親しみのあるものにしてくれました。
書かれた当時、作者の清川さんは90歳です。
美しい女性の姿が見えるようです。
歳を重ねてさらに、面白がり、不思議がり、新な挑戦が出来てこそ、この美しさを得られるのでしょう。
私が一番、こうなりたいと思った一節をご紹介します。
「ひとつひとつの言葉をとことん吟味し、ここにはこの言葉しかない、というほどのギリギリの選択をして、原稿用紙に心を刻みつけるように書かれた文章は、たとえば極上の炊き方をされたごはんのように、粒が立って光って見える。イージーに書き流されたり、打ち流された文章は、活字がみんな寝ているように、私には見える」
言葉を音に換え、文章を音楽に換えて、私も粒が立ってひとつひとつの音が光って見える音を出したい、と思いました。
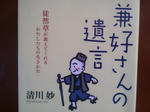
清川妙著『兼好さんの遺言ーー徒然草が教えてくれるわたしたちの生きかた』を読みました。
徒然草の言葉を手本に、生きてきた作者の体験が、徒然草を分かりやすく親しみのあるものにしてくれました。
書かれた当時、作者の清川さんは90歳です。
美しい女性の姿が見えるようです。
歳を重ねてさらに、面白がり、不思議がり、新な挑戦が出来てこそ、この美しさを得られるのでしょう。
私が一番、こうなりたいと思った一節をご紹介します。
「ひとつひとつの言葉をとことん吟味し、ここにはこの言葉しかない、というほどのギリギリの選択をして、原稿用紙に心を刻みつけるように書かれた文章は、たとえば極上の炊き方をされたごはんのように、粒が立って光って見える。イージーに書き流されたり、打ち流された文章は、活字がみんな寝ているように、私には見える」
言葉を音に換え、文章を音楽に換えて、私も粒が立ってひとつひとつの音が光って見える音を出したい、と思いました。
PR
安達かずみです。
林真理子著『白蓮れんれん』の点訳データ化校正、全6巻、面白くてあっという間に終わりました。
柳原白蓮の生涯を小説にした本です。
読みながら、女の弱さは、自分を生かしてくれる人に寄りかかるところ、自尊心を満足させるために自分の外側の付属物をどう高めるかに腐心するところ、そんなことを、いやというほど感じていましたが、最後になって、その自尊心も付属物もすべて手放さねばならなくなってからの、ただひとつの命の塊となって、生き抜き始めてからの白蓮さん。この強さが、勝つ人間の条件なんだろうな、と思いました。
寄りかかれる状況下では、どうしても寄りかかってしまいますが、人生の中で、なにも頼れない最悪の時は、どの人にもあるような気がします。
その時に勝者になるチャンスが来るのかもしれません。
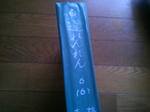
林真理子著『白蓮れんれん』の点訳データ化校正、全6巻、面白くてあっという間に終わりました。
柳原白蓮の生涯を小説にした本です。
読みながら、女の弱さは、自分を生かしてくれる人に寄りかかるところ、自尊心を満足させるために自分の外側の付属物をどう高めるかに腐心するところ、そんなことを、いやというほど感じていましたが、最後になって、その自尊心も付属物もすべて手放さねばならなくなってからの、ただひとつの命の塊となって、生き抜き始めてからの白蓮さん。この強さが、勝つ人間の条件なんだろうな、と思いました。
寄りかかれる状況下では、どうしても寄りかかってしまいますが、人生の中で、なにも頼れない最悪の時は、どの人にもあるような気がします。
その時に勝者になるチャンスが来るのかもしれません。
安達かずみです。
先日のフルートのレッスンで先生は、メロディを吹く時に、「一人で立つ」ことの大切さを指摘して下さいました。
二重奏をしていて、リズムやハーモニーの役割をする時とメロディを担当する時があります。
先生と吹いていると、つい、どこを吹いていても、邪魔にならないようにと恐る恐る吹いてしまいます。
私がメロディの時に、それを言われました。
助けることも、代わることも出来ない、自分一人で主張しなくてはならない、リズムやハーモニーは応援でしかない、と。
そうなんです。
なんとなく、流れに身を任せて、自分はどうしたい、とか、こういうドラマを作っていこうというような積極性を落っことしてしまうんです。
それを先生は「生命力」ともおっしゃいました。
音楽も人生も「一人立つ、生命力」こそ身に付けなければならないもののようです。
先日のフルートのレッスンで先生は、メロディを吹く時に、「一人で立つ」ことの大切さを指摘して下さいました。
二重奏をしていて、リズムやハーモニーの役割をする時とメロディを担当する時があります。
先生と吹いていると、つい、どこを吹いていても、邪魔にならないようにと恐る恐る吹いてしまいます。
私がメロディの時に、それを言われました。
助けることも、代わることも出来ない、自分一人で主張しなくてはならない、リズムやハーモニーは応援でしかない、と。
そうなんです。
なんとなく、流れに身を任せて、自分はどうしたい、とか、こういうドラマを作っていこうというような積極性を落っことしてしまうんです。
それを先生は「生命力」ともおっしゃいました。
音楽も人生も「一人立つ、生命力」こそ身に付けなければならないもののようです。
安達かずみです。
手打ちの点訳本曽野綾子著『中年以後』のデータ化が終わりました。
人も物も生き物である。いつかは必ず死ぬか滅びる運命にある。その存在を役立てることは、人間の大きな義務である。この世に存在したものは、必ずどこかで喜んで受け入れられていなければならない、と思う。
「こんなもの」と言われたり、働く場もなく、腐らせて捨て置かれるのではないように使いきらなければならない。
誰がいなくても世界は着実に動いていくのである。中年以後に意識すべきことは、自分がいなくても誰も困らないという現実を認識することである。
中年以後がもし利己的であったらそれはまことに幼く、醜く、しらけたものになる。老年は自分のことだけでなく、人のことを十分に考える歳だ。自分の運命だけでなく、人の運命さえも、もしそれが流されているならば、なんとかして手をさしのべて救おうとすべき年齢なのである。
正しさとは他者に対する負い目を自覚することだという。
私達はさまざまなものに育てられた。そこから受けた負い目を支払うのが正しさであると、トマス・アキナスは規定する。
などなど、もしかして、点字図書館の事務員さん、私に読ませるためにこの本選んでくれた?

手打ちの点訳本曽野綾子著『中年以後』のデータ化が終わりました。
人も物も生き物である。いつかは必ず死ぬか滅びる運命にある。その存在を役立てることは、人間の大きな義務である。この世に存在したものは、必ずどこかで喜んで受け入れられていなければならない、と思う。
「こんなもの」と言われたり、働く場もなく、腐らせて捨て置かれるのではないように使いきらなければならない。
誰がいなくても世界は着実に動いていくのである。中年以後に意識すべきことは、自分がいなくても誰も困らないという現実を認識することである。
中年以後がもし利己的であったらそれはまことに幼く、醜く、しらけたものになる。老年は自分のことだけでなく、人のことを十分に考える歳だ。自分の運命だけでなく、人の運命さえも、もしそれが流されているならば、なんとかして手をさしのべて救おうとすべき年齢なのである。
正しさとは他者に対する負い目を自覚することだという。
私達はさまざまなものに育てられた。そこから受けた負い目を支払うのが正しさであると、トマス・アキナスは規定する。
などなど、もしかして、点字図書館の事務員さん、私に読ませるためにこの本選んでくれた?
安達かずみです。
昨日、フルートのレッスンの後、先生との雑談のなかでこんな話になりました。
先生のお父さんが亡くなる少し前、お父さんと一緒に住んでいた先生のお姉さんが旅行に行くため、先生がお父さんと過ごすことになった時のことです。
お父さんは92歳。お父さんは、自分がいつどうなるか分らないのに、お姉さんが旅行に行ったことを怒っていたそうです。
「92だよ」先生は、あんたもう十分でしょ、って内心思ったそうです。
でも、そうじゃないんだ。生きているってことは「今と今から」しかないんだよ。それはどんなに年をとっても、どんな状態でもなんだよ、と。
そんなこと当たり前だと思ったのですが、帰りのバスのなかでこの話を思い返してみると、自分も、「この人はもういいでしょう」という思いで相対している人がいるな、と、気づきました。
今日はお詫びする思いで、三人
のお年寄りを訪ねて、いっぱい話を聞きました。いっぱい笑いました。
昨日、フルートのレッスンの後、先生との雑談のなかでこんな話になりました。
先生のお父さんが亡くなる少し前、お父さんと一緒に住んでいた先生のお姉さんが旅行に行くため、先生がお父さんと過ごすことになった時のことです。
お父さんは92歳。お父さんは、自分がいつどうなるか分らないのに、お姉さんが旅行に行ったことを怒っていたそうです。
「92だよ」先生は、あんたもう十分でしょ、って内心思ったそうです。
でも、そうじゃないんだ。生きているってことは「今と今から」しかないんだよ。それはどんなに年をとっても、どんな状態でもなんだよ、と。
そんなこと当たり前だと思ったのですが、帰りのバスのなかでこの話を思い返してみると、自分も、「この人はもういいでしょう」という思いで相対している人がいるな、と、気づきました。
今日はお詫びする思いで、三人
のお年寄りを訪ねて、いっぱい話を聞きました。いっぱい笑いました。

